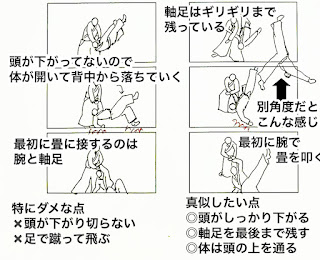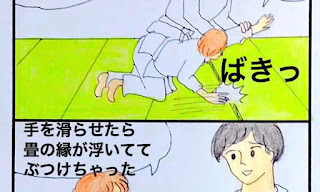2024.1.31 2025.7.11
カッコいい黒帯仕草⑥~脇をしめる・肘を絞る
脇をしめるということは、脇と腕を密着させることだけではない。脇と腕に空間があっても、脇と腕が結びついていればよい。腕が脇と結んでいるということは、腕が体幹、とりわけ腰と結んでいることであり、相手は腕をつかんでいるつもりでも、実際は腰や体幹を掴んでいることになる。
脇をしめる=腕が脇と結んでいる状態、腕が体幹・腰と結んでいる状態
なのですね。
…で、どうすれば、結べるようになるんだろ。
腋の下をパカッと開いて、スキマを空けることが前提の動作では、どうやって脇を締めれば、いいのでしょうか?
答は、肩甲骨にあるんです。
「脇を締める」というのは、肩甲骨を締めることなんですね。
正確には、左右肩甲骨の下部、下端を締め、寄せて近づけるということです。
⇒ 剣道の構え③肩甲骨の力を最大限に引き出す「脇の締め」とは!? 剣先の向きも修正する (俺流の刃)
では、「脇を締める」ポイントまとめに入ります。
上腕外旋アプローチ1:肩甲骨を引くような意識で肩を外旋する。この時、肩に力を入れないようにし肩を下げる。
上腕外旋アプローチ2:胸部を軽く張ってみる。肩を下におろす
脇を締めると体幹の力が上手く使えるようになる。脇の締め方は腕を体にくっつけるとか腕に横方向の力を加えるのではなく腕を捻って肘の内側を正面に向けるだけ。この状態なら腕を真っすぐ伸ばしたり横に開いても脇が締まり肩甲骨と腕が連動してくれます。
肩甲骨を使った打突をするには肘の内側を打突の瞬間に天井へ向くように絞るそうすると骨格で脇を締めるので肩に力が入らず肩甲骨が動く
広背筋や上腕骨よりも、肘の方がまだ意識できそう!
そう言えば、T先生の天地投げの天(上側) の腕、いつもすごく肘が絞られてる。
つかまれる瞬間、先生の肘はぐっと自分の体の前面にある。
そして、肘が自分の体の幅から外側に出ることなく、上がっていく。
「上腕骨の外旋」も、やってみると、肘が体の前に来る気がする!同じことなのかも?!
以前、Y先生に「腕は自分の肩幅から外に出さないよ」と言われました。
その時、私は腕を広げて、肘も手より更に外側に張っちゃってた。明らかに変だ。
腕は自分の体の幅より内側、肘も内側に絞っておきたい。
そして、肩甲骨同士を下方向・真ん中に寄せる。
TY先生が両腕を広げる、いつもの動きの時「腕を広げてるだけに見えるけど、実は肩甲骨を寄せてるんだ」と先輩言ってた。
肩甲骨から操作できれば、どんなに腕広げても、脇はしまるんだろう。
人間の体は奥が深い。
自分の体を意のままに操作できるようになったら、合気道も上手くなるし、普段の動きも楽になるんだと思う。
現段階では、肘と腕の位置を意識する程度が精一杯だけど、少しずつ改善したいです。
稽古の段階 ~ 固体・柔体・流体・気体
ある先輩は、岩間 (合気会茨城支部) 合宿に参加したことがあるそうです。
岩間と言えば、開祖が晩年を過ごした地!合気神社もある!いつか行ってみたい。
(追記:2025年は合気神社例大祭と岩間合宿に参加しました!聖地巡礼みたいで楽しかったです。)
岩間の道場では稽古が4段階あるそうです。
固体、柔体、流体、気体。
固体がガッチリつかむ系のかたい稽古。
この稽古をしっかりやらないと、その先の稽古には進めない。
柔体・流体は、相手の起こりをとらえて、つかまれた時には体捌きで、相手を自分の流れの中に入れる感じ?
気体が、触らない系の気の世界・精神の世界のことみたい。
2 岩間に残されている指導方法
正しい形(型)をゆっくり、丁寧に指導する。
正しい形(型)を徐々にスピードと強度を高めるよう指導する。
しっかりと打たせる、掴ませる(固体)稽古法を充分に行い、次の段階が気の流れ(柔体・流体)の稽古法に移る。
形(型)が崩れたら、基本を指導する。
精神性を高めることにより、最後には型が無くなる。(武の極意は形はない、心自在に生ず、これ極意なり)
固体の稽古で、白帯はまず基本の型をしっかり学ぶ。
黒帯になったら、型を効かせるための技術を身につける。
たくさんある中で、今日教わったのは以下の通り。
※ちなみに、岩間に行った先輩に教えてもらっただけで、これら= 岩間かどうかまでは分かりません。
- 作業台 (自分の作業台でとらせる。バレないように、さり気なく。体で入ったり半身を上手く使い、自分の作業台=相手は力入らない位置で)
- 崩し (重さをかける。相手を前のめりにさせる。ずっと相手を崩したまま、動く)
- 折れない腕
- 一体化 (近くで、あるいは離れた状態で。離れてる時は、折れない腕で)
- 重心 (相手の重心を捉える、相手の重心に向かって落とす)
型と技を身につけると、流れの中でも動けるようになる。
固体・柔体・流体の先に気体の世界がある。
4 稽古の順序
1,正しい形(型)をゆっくり、丁寧に。除々に烈しく
2,初心者を中心にして
3,“気の流れ”の稽古は三段以上
岩間では、気の流れ = 柔体・流体。その稽古は三段以上とあります。
柔体・流体 下手したら気体 の稽古、全然できなくて悲しかったけど、岩間基準だと私なんかまだ稽古もさせてもらえない立場。
できなくて当然だわ。
まずは、基本の型と技をしっかり身につけたいと思います。